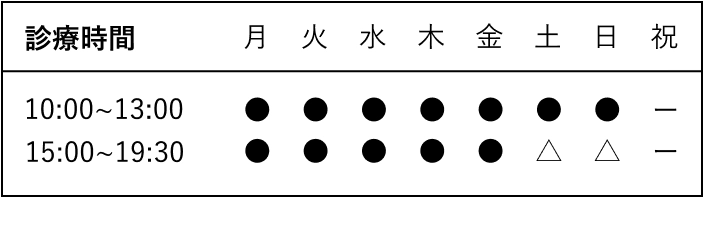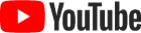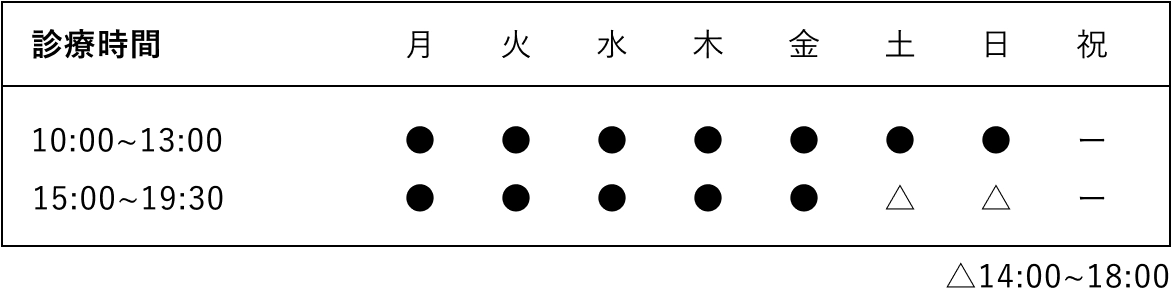- 新宿の歯医者なら新宿ルーブル歯科・矯正歯科TOP
- お知らせ一覧
- 虫歯
- 虫歯じゃないのに歯が痛いときに考えられる9つの原因
虫歯じゃないのに歯が痛いときに考えられる9つの原因

虫歯の症状がないにも関わらず、歯がズキズキ・キーンと痛むことはありませんか?虫歯は少しずつ歯を侵食する病気ですが、痛みを感じるのは歯の中に通っている神経のため、虫歯以外の症状でも痛みを感じるケースがあります。
ここでは、虫歯じゃないのになぜか歯が痛むときの原因と、治療が難しいとされている理由について紹介します。虫歯になっていないのに歯が痛いと感じた経験がある方や、虫歯以外の痛みについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
虫歯じゃないのに歯が痛い原因

虫歯じゃないのに歯が痛いときは、9つの原因が考えられます。それぞれ痛みの原因となる症例や行動が関わっていますが、どのような問題が考えられるのでしょうか。
原因①歯の神経の露出
虫歯ではなくても、歯に穴があいてしまい神経が露出、または神経に近いところまで歯が削れてしまうと、外の温度変化や刺激を敏感に感じ取ってしまいます。
歯の神経は、虫歯だけではなく「刺激」を伝えるものです。刺激を感じ取って歯の以上や違和感に気づけるため、少し露出しただけでも「歯がすり減っている」などのアラートとして機能しているのです。
症例としてはほとんどみられないものの、歯科治療の影響で神経が露出するような場合もあります。
原因②細菌による炎症
お口の中には無数の細菌が棲んでおり、細菌同士のバランスが崩れると虫歯や歯周病といった病気にかかりやすくなります。
細菌による炎症としては「歯周病」が広く知られていますが、歯以外の場所に炎症が起きて刺激が歯に伝わった場合は、虫歯のような痛みが出現します。「非歯原性歯痛(ひしげんせいしつう)」と呼ばれる症状です。
非歯原性歯痛は歯のほかにお口の中、喉、あご(筋肉を動かしたとき)にも起こります。電気が走るような痛みが特徴で、発作的という特徴もあります。
どこに炎症が起きているのか、また炎症ではない場合(精神疾患や心臓疾患など)も考えられるため、専門医での検査が必要です。
【関連記事】歯周病と虫歯の違い|押さえておきたいそれぞれの原因・症状・治療法
【関連記事】歯周病は放っておくと危険!?歯肉炎との違いや治療法を解説
原因③歯並び
噛み合わせの悪さにより、特定の歯にばかり力がかかってしまうケースも歯痛の原因になります。
ズキンズキンと重く響くような痛みがあるとき、特定の歯が圧迫されていないか、噛み合わせが悪いためにおかしな力がかかっていないかを確認しましょう。
歯並びは生まれもってのもので、噛み合わせの悪さは虫歯のようにすぐに解消することができません。歯科医とよく話し合い、抜歯や歯を削るといった処置のほか、矯正治療なども選択肢の一つとして考えていくと良いかもしれません。
原因④口内炎
お口の中の歯や歯茎以外の場所にできることが多い口内炎は、「ウイルス性口内炎」と、「カタル性口内炎」に分けられます。
このうち、ウイルス性口内炎は歯茎にも炎症が及ぶ場合があります。歯茎まわりの炎症はそれ自体が痛みをもつものですが、歯に近い場所のため歯痛と錯覚しやすい特徴があります。
口内炎というと頬の内側や唇の裏側などにできるイメージがありますが、歯茎のそばに口内炎があると痛みの範囲があいまいになるため、気になる症状や痛みは専門医に相談してください。
原因⑤神経痛や片頭痛
顔や口、歯に現れる神経痛の症状にも注意が必要です。多く見られるものとして「三叉神経痛」と呼ばれる痛みが現れる場合があります。
三叉神経痛は歯を磨くだけで激痛が一瞬走るような、虫歯や歯周病とは関係がなくても神経が痛む病気です。歯医者で検査しても問題がみられなければ、神経痛の疑いもあるため専門医を受診しましょう。
突発的に現れる頭痛症状である「片頭痛」も、ズキズキと痛みながら歯にまで影響してくるため、片頭痛の症状をお持ちの方は注意が必要です。
原因⑥精神的ストレス
歯が直接的な原因ではない歯痛は「非歯原性歯痛」と呼ばれます。この歯痛には、仕事や人間関係、その他のストレスが関わっている場合があります。
ストレスを受けると、口の中からは唾液が減って乾いた状態になり、滑らかさが失われます。これにより口内炎や歯周病が発生しやすくなり、痛みに繋がることがあります。
また、食いしばりや歯ぎしりのようなストレス性の行動も歯痛の原因になるため、不安感が強い場合は専門医に相談のうえ、かかりつけの歯医者とも連携して治療の方向性を決めていきましょう。
原因⑦口腔がん
口腔がんは口の中にできるがんの症状であり、唇などのしびれや神経障害をきたします。
特に口の中の神経系に及んでくると、虫歯や歯周病がみられなくても歯痛を起こすことがあります。口腔がんを発見する目安としては味覚の異常や口内炎などが挙げられますが、他にも普段と違う症状があればすぐに専門医を受診してください。
原因⑧歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりは、奥歯で発生するケースが多いトラブルです。日中の起きている時間帯は意識的にコントロールできるため症状を自覚しにくく、就寝中に多く発生します。
原因としてはストレス、身体的な不調、噛み合わせの問題、眠りの浅さといった原因が考えられ、飲酒やカフェインの摂取によっても起きる可能性があります。
頻繁に歯ぎしりや食いしばりをするようであれば、マウスピースの装着や矯正治療などを検討したいところですが、歯科医と相談のうえで治療方法を検討してください。
原因⑨咀嚼筋の炎症
咀嚼筋は、ものを噛み砕く(咀嚼する)ときに動かす筋肉です。主に顎を動かす筋肉で、ここが酷使されて疲労すると痛みの発生元・トリガーポイントになり、歯痛を引き起こすとされています。
ただし、人間の場合は咀嚼筋の痛みよりも顎関節症がまず疑われます。顎まわりの検査や確認、治療が行える口腔外科を受診するか、口腔外科を併設している歯科クリニックを受診してください。
原因⑩歯周病
歯周病とは、歯を支えている歯茎や骨が細菌の感染により破壊される疾患です。初期段階では自覚症状がほぼないため、気づかないうちに症状が進行します。
歯周病の原因は、歯垢(プラーク)と呼ばれる歯の表面に付着する細菌の塊です。歯垢の中に含まれる細菌や免疫反応が原因で、歯茎が腫れや出血が生じます。
症状が進行すると歯を支えている骨が溶け、歯がぐらつきます。この段階まで進行すると噛む際に痛みを伴うため、虫歯と勘違いするケースも少なくありません。
放置すると最終的には歯を失う可能性もあるため、定期的に歯科検診を受けることが重要です。
なお歯周病の予防は、毎日の丁寧な歯磨きが基本です。歯間ブラシやデンタルフロスも併用し、歯と歯の間や歯と歯茎の境目まで清掃しましょう。
【関連記事】歯周病が手遅れになったときの症状とは?セルフケアで予防はできる?
原因⑪歯髄炎
歯髄炎とは、歯の中心部に位置する歯髄部分に炎症が起こる病気です。歯髄は神経や血管が集まっている場所で、歯に感覚を与え栄養を供給する役割を担っています。
歯髄炎のおもな原因は虫歯です。虫歯が進行し歯の内部にまで達すると、細菌が歯髄に感染し炎症を引き起こします。
初期の段階では冷たいものがしみる程度ですが、進行すると激しい痛みを感じます。
放置すると歯髄が死んでしまい、根尖性歯周炎へと発展するため危険です。根尖性歯周炎になると歯の根の周りの骨が溶け、最終的には歯を失います。
なお歯髄炎の治療法は、進行の度合いで異なります。初期段階なら薬で炎症を抑えられますが、症状が進行している場合は、歯髄を取り除く根管治療が必要です。
早期発見と治療が大切なため、症状を感じたら早めに歯科医師に相談しましょう。
原因⑫象牙質知覚過敏
象牙質知覚過敏とは、歯の表面のエナメル質が薄くなり象牙質がむき出しになることで、痛みを感じる症状です。
冷たいものや甘いものといった食事のほか、歯磨きなどの刺激でも痛みを感じます。象牙質には神経につながる管が無数にあり、刺激が神経に伝わることで痛みが生じるためです。
なお、歯は外側からエナメル質、象牙質、歯髄の3つの層で構成されています。エナメル質は歯を保護する役割を担い、削れたり薄くなったりすると知覚過敏が起こります。
象牙質知覚過敏のおもな原因は、歯周病による歯茎の退縮や歯ぎしりなどによる歯の摩耗です。また加齢や歯磨きが原因の場合もあります。
知覚過敏を予防するためには、歯ブラシの毛先が硬いものを避け、優しく歯磨きしましょう。また歯科医院で定期的に歯をクリーニングするのもポイントです。
原因⑬親知らず
親知らずとは、一般的に10代後半から20代にかけて生えてくる歯のことです。正式には「第三大臼歯」と呼ばれ、一番奥に存在します。
親知らずが生える原因は、現代人の顎が小さくなったためです。硬いものを食べない影響で顎が小さくなり、親知らずが生えるスペースが十分ないためと考えられています。
なお、親知らずはまっすぐに生えないことが多く、周囲の歯に悪影響を及ぼします。磨きにくい場所にあるため、虫歯や歯周病になりやすいのも特徴です。
また親知らずが隣の歯を押して生えることで、歯並びが悪くなることもあります。
なお治療法としては抜歯が一般的ですが、必須ではありません。もし痛みや腫れなどの症状が生じた場合は、早めに歯科医に相談しましょう。
虫歯じゃないのに歯が痛いときの対処法
虫歯ではないのに歯が痛いときの対処法は、おもに以下の3つです。
- 痛み止めを服用する
- 患部を冷やす
- 口腔ケアを徹底する
痛み止めで対処する際は、痛み止めに含まれる成分に注目します。一般的には「ロキソプロフェン」の成分が、市販薬の中では効果が高いとされています。
また患部を冷やす場合は、冷たいタオルや冷却シートを使うのが効果的です。患部の血流が抑えられ、痛みを感じている神経への刺激が弱まります。
口腔ケアで対処する場合は、歯ブラシの選定や磨き方が重要になります。ただし虫歯や歯周病の進行を遅らせることはできても、根本的な治療にはなりません。
痛み止めの服用と患部の冷却も同様です。あくまでも応急処置に過ぎないため、痛みを感じたら早めに歯科医を受診しましょう。
では、それぞれの対処法を詳しく解説します。
痛み止めを服用する
虫歯の痛みに効果的な市販薬は、いくつかあります。購入時は以下の成分を参考に選ぶと良いでしょう。
| 成分 | 効果 |
| ロキソプロフェン | 市販薬もっとも一般的な成分で効果も高い |
| イブプロフェン | ロキソプロフェンと同様に効果が高い |
| アセトアミノフェン | 鎮痛効果はロキソプロフェンやイブプロフェンに比べると劣るが、胃への負担が少ない |
ロキソプロフェンは「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」の一種で、痛みや炎症を抑える効果を持つ薬です。頭痛や歯痛、生理痛や関節痛などさまざまな痛みに効きます。
またイブプロフェンもロキソプロフェンと同様に、さまざまな痛みに効果的です。アセトアミノフェンは鎮痛効果が劣るものの、胃への負担が少ない特徴があります。
いずれも説明書を読んだうえで、用法と用量を守り服用しましょう。
患部を冷やす
虫歯の患部を冷やして対処する際は、直接患部を冷やさないようにしましょう。氷を直接あてたり冷水を含んだりする方法は、歯や歯茎を傷つける可能性があるためです。
冷たいタオルや冷却シートを頬にあて、間接的に冷やすのがポイントです。痛みを感じ始めたタイミングで冷やすようにしましょう。
患部を冷やすことで血流が抑制され、神経への刺激が緩和されます。一時的ではありますが、痛みを抑えられるでしょう。
ただし患部を冷やしすぎると、かえって痛みが増すこともあります。1回あたり10〜15分程度を目安に、様子を見ながら冷やしましょう。
ただし冷やすことはあくまでも応急処置であり、根本的な治療にはなりません。また冷やしても痛みが引かない場合もあるため、痛みを感じた時点で早めに歯科医に相談しましょう。
口腔ケアを徹底する
口腔ケアの徹底により、虫歯や歯周病を予防できます。口腔ケアで重要なのが、毎日の歯磨きです。
参考までに、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と口腔ケアのポイントを紹介します。
| 種類 | 選び方・口腔ケアのポイント |
| 歯ブラシ |
|
| 歯磨き粉 |
|
なお歯磨きにかける時間は、最低でも毎回3分が目安です。ただし時間をかけすぎると歯や歯茎を傷つけたり、知覚過敏になる可能性があるため注意しましょう。
虫歯じゃないのに歯が痛いときの治療が難しい理由

「虫歯じゃないのに歯が痛い」という状態は、どの病院にかかれば良いのか判断に迷うところです。クリニックにとっても悩みどころであり、治療を進めずに様子見とするところも少なくありません。
治療がなぜ難しいのか、3つの理由をみていきましょう。
理由①原因不明のため
原因がまったくわからず、虫歯や歯周病でもなければ、原因がはっきりするまで様子見とする場合があります。
歯科だけで対処ができない場合、神経痛や頭痛、顎関節症といったさまざまな理由が考えられます。しかしどの部位が痛みを引き起こしているのかはっきりとしない状態では、患者さんご自身にそれぞれの病院を受診してもらう必要があります。
たとえば口腔がんの場合は、歯科だけでは対処しきれず耳鼻咽喉科や口腔外科の受診が必要になります。そこでがんの疑いが強いと診断されれば、口腔がんの専門医が所属しているクリニックや中規模以上の病院へと転院することになります。
原因がはっきりすれば治療が可能になるので、気になる症状は「よくわからないから」とそのままにせず、病院の受診で早期発見・早期治療に繋げることが大切です。
理由②患者の思い込みの場合があるため
患者さん自身が実感する痛みのなかには、強い思い込みが含まれているケースもあります。
一例として、ある歯医者で虫歯治療を受け、術後も歯が染みていた患者さんが、「治療が不十分だったのではないか」「治療が不十分だったのでまだ虫歯が残っていて染みているのではないか」と思い込むものです。
また、「削りすぎたせいで虫歯にかかりやすくなった」と過剰に心配してしまい、それが強い思い込みとなり痛みを発生させているようなケースも考えられるでしょう。
思い込みによる症状は、そのまま治療をすることはできません。治療が必要になるかどうかは画像診断などの検査を丁寧に行ってからの判断になります。
不安感が強い患者さんには、精密検査が可能な大病院を紹介したうえで検査を受けてもらい、後日その検査結果によって治療方針を決めていく方法もとられています。
理由③歯医者の誤った判断による治療実施のため
歯医者側が判断を誤って治療を実施し、その結果として歯痛が現れてくるケースもあります。たとえば、差し歯の治療のために歯を削る必要があり、歯を削ったところ範囲が大きく、歯が染みやすくなるような場合です。
神経が少しでも露出してくると電流が走るような痛みを感じるようになるため、歯医者の判断ミスや治療ミスによる歯痛の場合は、相当のアフターフォローが必要になります。
過去に受けた虫歯や歯茎の治療が原因の場合、患部を清潔にしてから詰め物や被せ物を入れ直しますが、神経に何らかの問題があれば根管治療になる可能性もあります。
しかし神経を取り除いてしまうと二度と元には戻せないため、原因がはっきりしない状態では治療が難しいのが実情です。
詳しい検査で歯痛の原因を調べよう

今回は、虫歯じゃないのに歯が痛いときの原因と、治療が難しい理由について紹介しました。
非歯原性歯痛は歯医者側の判断だけで治療が進められず、耳鼻咽喉科や脳神経外科といった歯科領域以外での検査が必要になります。ただし、検査の結果歯科で治療が必要(効果的)であると判断されれば、かかりつけの歯科クリニックで治療が進められます。
歯が痛むときは、どのような痛みなのか・既往症があるか・治療経験とその内容・歯痛以外の症状(筋肉痛や頭痛など)を医師に伝え、気になる箇所の早期発見と早期治療を行ってください。
新宿の歯医者「新宿ルーブル歯科・矯正歯科」では、無料でカウンセリングを行っています。歯に悩みがあり歯科受診を検討している方は、お気軽にご相談ください。
ご予約・ご相談はこちら
この記事を監修した人

医療法人社団ルーブル 理事長
愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。
「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。
【略歴】
- 愛知学院大学歯学部 卒業
- しんファミリー歯科 矯正監修
- 大手審美歯科クリニック 代診勤務医
- 医療法人清翔会 エスカ歯科・矯正歯科 院長就任
- 渋谷ルーブル歯科・矯正歯科 独立開業
- 医療法人社団 ルーブル設立 理事長就任
- 新宿ルーブル歯科・矯正歯科 開業
【所属団体】
- インビザライン社公認 ダイヤモンドプロバイダー
- インビザライン(マウスピース矯正)認定医
- インコグニート舌側矯正 認定医
- winシステム舌側矯正 認定医
- 日本矯正歯科学会 所属
- 日本成人矯正歯科学会 所属
- 日本顎咬合学会 所属
- 日本外傷歯学会 認定医
- 日本アンチエイジング歯科学会 所属
- 日本歯科審美学会 所属 他多数